実施報告:北大道新アカデミー2025後期総合コース
ワインは北から〜北海道の新たなフロンティア〜
北大道新アカデミーは、地域の「知」のために、北海道大学と道新グループが協力して2018年4月に開講した新しい学びの場です。2025年度後期総合コースは、ワインを切り口として、北海道大学北海道ワイン教育研究センターに所属する、農学研究院、地球環境科学研究院、メディア・コミュニケーション研究院の研究者と、水産科学研究院の研究者が、6回の講義を行います。
北海道を世界に通用するワインの産地にする取り組みが、北海道ワインバレー構想です。その拠点となる北海道大学の研究者が、ワインに関わる研究成果を紹介します。講義を聴くとワインの味わいが少し違ってくるかも?
第6回「ワイン用ブドウ栽培から考える北海道の気候」2025.11.22(土)
根本学客員教授(農研機構北海道農業研究センター上席研究員・農学研究院・北海道ワイン教育研究センター)
最終回の講義は、農業気象を専門にする根本学客員教授が務めました。北海道の気候と、ブドウの栽培やワインの味わいの関係がテーマです。フランスやアメリカなどの世界の主要なワイン生産国の気候と比べると、北海道は植物の生長に関係する有効積算温度が低い傾向があります。加えて、ブドウが育つ時期の降水量が多く、日射量は少ないです。北海道の冬の気温は他の生産地に比べて低く、積雪があるのも特徴です。
冬の寒さと積雪は北海道のブドウ栽培に影響を与えています。まず、北海道のブドウ栽培では、冷涼な気候と厳冬期の寒さに適応した品種が求められます。そして、北海道では、ブドウの収穫が終えたら、根雪になる前に剪定を行い、ブドウが冬を越せるように、雪に埋める「枝下ろし」の作業を行わなければなりません。春になったらブドウの「枝あげ」を行います。積雪がない地域では不必要な農作業が北海道のブドウ栽培では生じます。ブドウを雪に埋めるため、ブドウの木の根元や曲げた部分に、雪の重さで損傷が発生することもあります。ブドウを雪の中に埋めることで「ブドウ根頭がんしゅ病」の病原菌が冬眠状態で保存されてしまい、病気が拡大することもあります。また、北海道では6月でも最低気温が0度以下に下がり、遅霜が発生することもあります。ちょうどブドウの芽や葉が生長する時期の遅霜は、ブドウの生育を阻害します。
冷涼な北海道では、ブドウの果実の成熟が十分に進む前に収穫を行うこともあり、果実に酸が残る傾向があります。そのため、北海道のワインは、アルコール度数が比較的低く、軽やかで、酸味の豊かな味わいが特徴です。北海道は2018年、山梨県に次いで2番目に、ワインの地理的表示(GI:Geographical Indication)の認定を得ました。北海道GI認定は北海道産のブドウを100%し、北海道で醸造が行われ、酸度などの基準を満たしたワインに与えられます。北海道の気候と北海道ワインの関連が明らかになる講義でした。

第5回「北海道産ワインのための土づくり:土壌中の根系分布の特徴」2025.11.8(土)
柏木淳一講師(農学研究院・国際食資源学院・北海道ワイン教育研究センター)
柏木淳一講師は土壌の専門家です。ブドウ園の土壌とブドウの根の生長について2017年から研究を始めました。最初に土壌に関する説明が行われました。「土」は何かが生えていることを意味する象形文字です。「壌」は豊かで芳醇であることを意味します。地球全体でみると、土壌は直径約1万3000キロメートルの地球を覆う、厚さ18センチの柔らかな薄皮です。有限の土壌が生産する動植物が人類の生存を支えています。私たちは土壌に生かされているといっても過言ではないでしょう。土壌を分析する観点として、砂・シルト・粘土の割合で決まる土性、固相・液相・気相の割合を示す三相分布、そして保水性があります。保水性は土壌が保持する水分量に関係します。砂地の水はけがよいように、土性は保水性と関係します。土壌が含む水分が多くなると、気相の割合が減少し、植物の根は呼吸ができなくなり枯れてしまいます。一方で、土壌の水分が減りすぎると、根は水分を吸い上げることができなくなります。土壌の水分量は植物の生長を決める要因のひとつになります。ブドウは乾燥した気候や土壌を好みます。湿気の多い土地では、ブドウに病気が発生しやすく、実が熟すタイミングも遅れがちになります。そのため、ブドウ栽培では土壌中の水を適切に管理することが不可欠です。柏木講師は、北海道のブドウ園の土壌とブドウの根の分布の関係を調べました。調査の結果、ブドウの根は地下1メートルまで及んでいました。土壌が固くなると、そこに生える根は少なくなります。しかし、土壌が固くても隙間や割れ目があるれば、根はそこに入り込んで生長することができていました。土壌の深い部分では含まれる水が多くなります。水分が多いと、ブドウは根を張ることができません。ブドウの根をより深く育て、品質の良いワインを作るためには、ブドウ園の排水改良が効果的です。北海道ワイン生産を支える土壌の役割を知ることの講義でした。
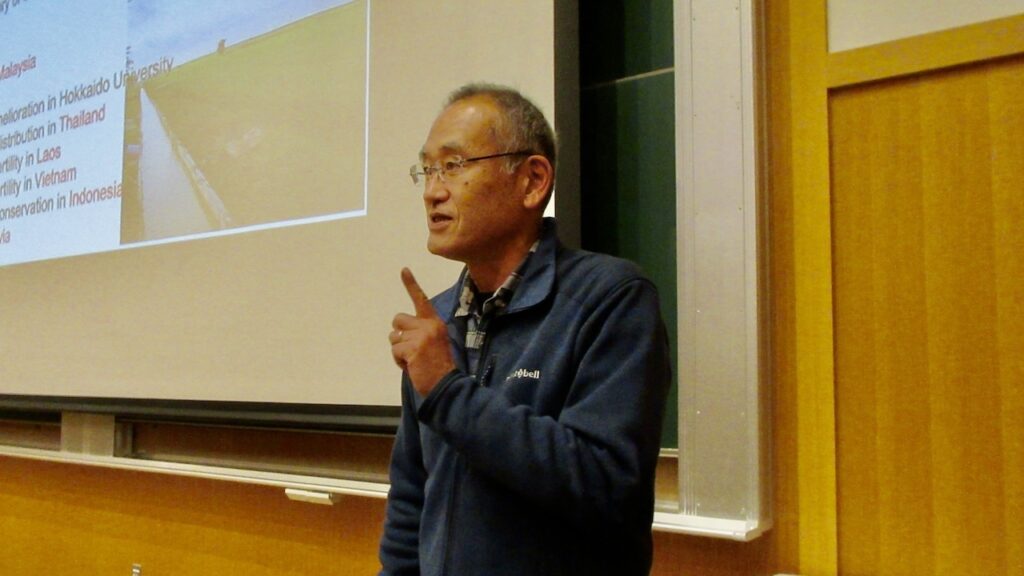
第4回「ワインに合う! 美しく美味しいカキを作るための動きの研究」2025.11.1(土)
富安信助教(水産科学研究院)
富安信助教は海洋測定分野の専門家です。カメラやセンサーを使って、漁業や生物の研究をしています。富安助教は今回の講義のために、水産学部のある函館キャンパスから札幌キャンパスに足を運んでくださいました。白ワインとカキの組み合わせは、ワインのマリアージュの王道です。生ガキと一緒にお酒を楽しむオイスターバーも身近なものになってきました。オイスターバーでは、カキの美味しさはもちろん、殻の長さ、高さ、幅のバランスがとれた美しいカキが求められています。富安助教は美しいカキの養殖法の研究成果を紹介しました。カキの養殖方法の1つであるカルチ法は、カキの幼生を大量にホタテ貝に付着させて、海水の下に垂らして育てます。この方法で育てたカキは、殻が細長く成長します。もう1つの、シングルシード法はカキを専用のバスケットに入れ、ひと粒ずつ育てる方法です。この方法で育てると殻が丸みを帯び、身入りが良くなり、甘味・うま味が強くなる特徴があります。富安助教はシングルシード法で用いられるバスケットの形状に伴うカキの「動き」の違いが、その形状に与える影響を調査しました。干潮の時にカキが海面に出ることで、揺れが生じる吊り下げ式と、恒常的にカキが海面下にあることで、揺れ続けているフロート式のバスケットで比較したところ、フロート式のバスケットで育てたカキの方が、殻のバランスがよく、肉厚なカキができることがわかりました。また、カキはバスケットの中で貝殻を開閉しています。開閉のタイミングは、吊り下げ式とフロート式で変わらず、満潮の時に開き干潮の時に閉じることがわかりました。一方、短い間隔で殻を開け閉めする連続スパイクと呼ばれる現象は、吊り下げ式のバスケットで生じていました。カキが連続スパイクを起こすときは、カキにストレスがかかっていることが知られています。富安助教はストレスの強さが、カキの身肉の成長に影響を与えている可能性を示唆しました。ワインとカキ、土のものと海のものが掛け合わされることで、新たな研究や産業が生まれる可能性があることを感じさせる講義でした。

第3回「化学と発酵を使ったブドウとワイン・チーズづくり」2025.10.25(土)
川口俊一准教授(地球環境科学研究院・国際食資源学院・ワイン教育研究センター)
総合ワインコース第3回の講義は川口俊一准教授が務めました。川口准教授が行っている、ワインづくりに関連する複数の研究が紹介されました。最初は、地球温暖化のブドウに与える影響です。札幌では、2017年から2023年の間に1.5度気温が上昇しました。さらに2024年から2025の間にも1.5度上昇しています。気温の上昇は植物の発育に影響を与えます。高温は植物の中の水分の発散を促進します。すると植物中の水の移動にともなって土壌の栄養が移動して茎や葉の発育に使われてしまい、果実の発育のころには土壌の栄養が足りなくなってしまいます。これを防ぐためには、従来よりも多めに肥料を与える必要があります。川口准教授は生産者に対し、科学的なデータに基づく施肥の方法を提案しています。次は、土壌改良による苗木育成の研究です。北海道は低温のため挿し木のブドウは冬が越せません。そこで川口准教授は、甲殻類の殻の粉末、キトサンを用いて土壌を改良する研究に取り組みました。これまでのキトサンは価格も高く、土壌改良にかかる時間も半年ほどかかりました。川口准教授が開発した改良型キトサンは従来に比べ少量かつ短時間で土壌を団粒化し、柔らかく、ふかふかにします。この土壌で育てた挿し木のブドウは、発育がよく、冬を越すこともできるようになりました。最後に、おいしさの数値化です。おいしさは味覚・嗅覚・食感・見た目によって構成されます。川口准教授は、味覚センサやにおいセンサを用いて、ワインの味わいや香りを数値化する研究を進めています。人は食べ物に含まれる化学物質が舌や鼻にある受容体に触れると、その情報が電気信号となり脳に伝えられて、味を認識することができます。味覚センサや嗅覚センサを使うと、ワインと料理のマリアージュについて、数値を用いて説明することができるようになります。また、食感センサと味覚センサの組み合わせにより、大豆からチーズを作る技術を紹介されました。川口准教授の語り口に、笑いも起きる楽しい講義でした。

第2回「ワインのマーケティング」2025.10.11(土)
中川理教授(メディア・コミュニケーション研究院・北海道ワイン教育研究センター 副センター長)
北海道ワイン教育研究センター 副センター長を務める中川理教授は、性・年齢構成比に基づく信頼性の高い大規模定量調査を消費者を対象に行っています。客観的に分析された調査結果をワインの生産者に伝えることで、消費者のニーズに沿った北海道のワインづくりを支援しています。今回の講義では、中川教授の行った調査結果がいくつか紹介されました。20歳から69歳の消費者を対象とした調査では、ワインをよく飲むのは60代で、20代はほとんど飲まないことが明らかになりました。ただワインをほとんど飲まない人の中でも機会があれば飲みたいと答える人が約6割います。この結果は、若い世代には、ワインの潜在的なニーズがあることを示唆しています。また、ワインの飲用者の約4割がスパークリングワインをもっとも好きなワインとして挙げているのに対し、日本でのスパークリングワインの生産量はわずか4%に過ぎません。スパークリングワインは、冷涼な北海道の気候にあったワインといえるため、今後、多く造られていくことが期待されます。同様に、ワインの味わいや香りについても消費者とワイン生産者の重視する点でギャップがみられます。ワインの飲用者は甘味のあるワインを好むのに対して、北海道の生産者は産地特性から酸味のあるワインづくりを行う傾向があります。今後の気候変動により甘味の強いワインの生産もしやすい環境になることが想定されるため、消費者ニーズも踏まえた複数のラインアップを提供することが考えられます。北海道大学の学生を対象とした人気講義「北海道サスティナブルワイン学」の履修学生に対する調査では、ワインについて学習することで、積極的にワインを選んで飲む人が増えたことが確認されました。ワインについて学び知識を深めることは、ワインに対する消費行動にも影響を与えています。ワインに関する学習や試飲会の体験機会を準備することは、ワイン市場の活性化につながるといえます。

第1回「北海道のワイン:サステイナブルテロワールを目指して」2025.9.20(土)
曾根輝雄教授(農学研究院・北海道ワイン教育研究センター センター長)
総合ワインコースの初回の講義は、北海道ワイン教育研究センター センター長を務める曾根輝雄教授が務めました。北海道大学のワイン研究を俯瞰することが目的です。キーワードは「サステイナブルテロワール」です。ワインは収穫したブドウの果汁のみで作られ、その発酵にはブドウに付着した酵母が関係しています。地域の気候や土壌に応じてブドウの種類も変わります。ワインは土地の風土を反映しています。ワイン産業が、地域の食品産業や観光業に波及し、経済効果や雇用効果をもたらし、それらが課題解決につながり地域を持続的にしていくことが、曾根教授の提案する「サステイナブルテロワール」です。2000年まで7軒だった北海道のワイナリーは、2025年9月現在、その10倍以上の、73ワイナリーを数え、都道府県の中では第3位、ワインの生産量は山梨県に次いで第2位になっています。北海道はワインのフロンティアです。一方、北海道のワイナリーの経営やワインの品質はまだ安定しているとはいえません。北海道のサステイナブルテロワールを牽引し、北海道の持続性を高める拠点が、2022年4月に発足した北海道ワイン教育研究センターです。講義では、2024年9月にオープンした有料で試飲のできる「北大ワインテイスティング・ラボ」や、旧昆虫標本庫を改修した「ワイン熟成庫」や、北海道ワインアカデミーの取り組みが紹介され、受講者の関心を集めていました。
