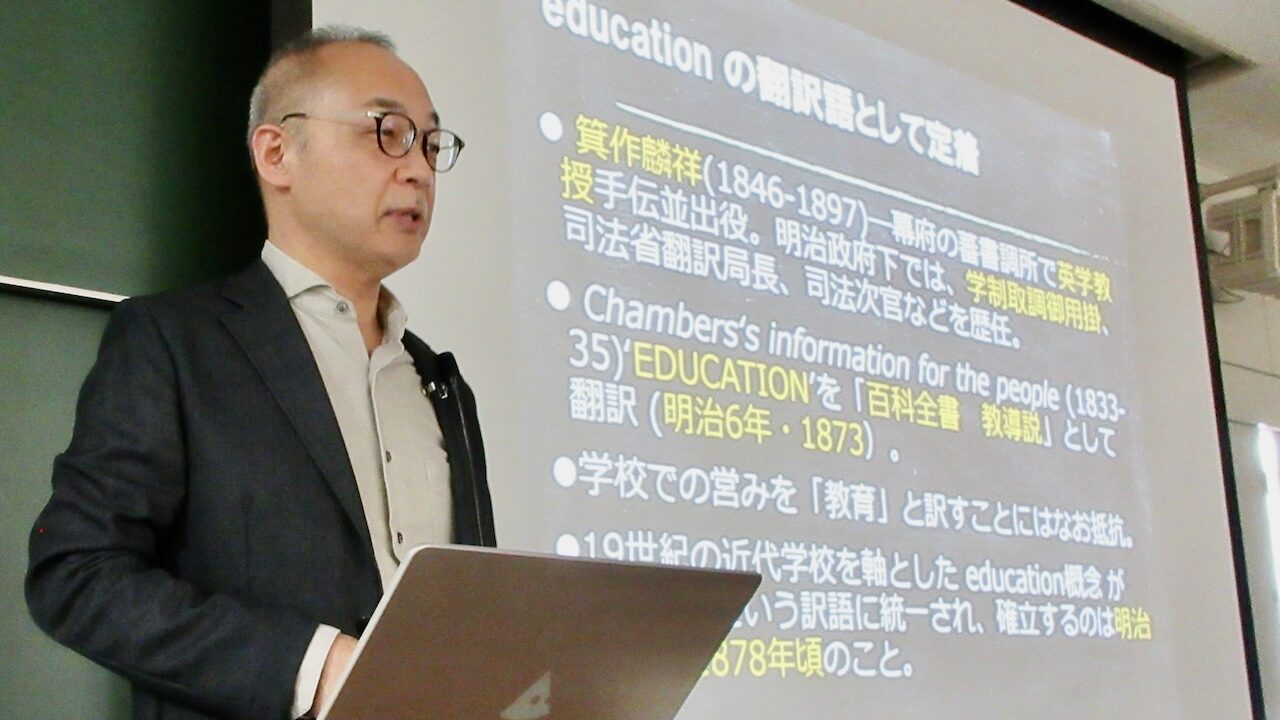実施報告:北大道新アカデミー2025前期文系コース
「学習」とは何か 学びを深める学びを学ぶ
北大道新アカデミーは、地域の「知」のために、北海道大学と道新グループが協力して2018年4月に開講した新しい学びの場です。2025年度前期文系コースは、北海道大学大学院教育学研究院の研究者が「「学習」とは何か 学びを深める学びを学ぶ」と題して8回の講義を行います。
【講義概要】学習することは私たちにとって身近な事柄のように見えますが、改めて考えると、それは様々な見方や考え方、性質や機能、領域や場面とかかわっていることがわかります。「学習」とは何か、「教育」とは何か、「学ぶ」とはどういうことかを切り口に、私たちの生活と学ぶことの関係や、誰もが学習する機会にひらかれた社会について考えます。
【『北大時報』掲載】
・北大道新アカデミー2025年前期コース開催報告が『北大時報』2025年8月号16ページに掲載されました。
第8回「「学びなおし」を考える」2025.6.28(土)
辻 智子教授(教育学研究院)
シリーズの最終回となる本講義は、研究院長の辻智子教授が行いました。講座全体を総括しながら、社会の様々な場面での多様な学びと人びとの暮らしとの関係を「成人教育」「社会教育」「生涯教育」「生涯学習」の視点から考えます。
辻教授は、教育を、人びとを抑圧する装置としての側面がある一方で、逆に、人びとを抑圧から解放する武器にもなりえるといいます。教育を解放の道に進めるためのヒントは「学びなおし」にあるのではないか。その考えを深めるために辻教授は「学習権」を挙げました。ユネスコは1985年に「学習権宣言」を採択しました。学習権宣言として結実する過程には、世界各国の識字教育と女性差別の撤廃を目指す国際的な取り組みがありました。この宣言は、学習権を、基本的人権のひとつであり、人間を「自分たち自身の歴史を創造する主体に変えるもの」とうたっています。これは、自分の人生の意味を問い直し、確認し、意味づけて、人生を豊かにするいとなみにも通じると考えられます。この学習権の考えは、イギリスをその発祥のひとつに持つ成人教育という考え方が含意していた、非職業的なリベラルアーツとしての学びとも呼応しています。そして辻教授は、日本の社会教育施設のひとつである公民館で行われる、公民館保育の事例を取り上げ、子どもたちが他の子どもや大人とかかわる体験を通じて、自分自身を捉え自立していくこと、その様子に触発されて、大人もまた、自らのものの見方や考え方のありようを見つめなおす機会を得ていることを紹介しました。今、私たちに必要なのは、職業スキルを高める「リスキリング」のみに回収されない「学びなおし」に目を向けることであり、「人生の意味を問いなおし、人生を豊かにするための学び」を「学びなおす」ことかもしれません。今回の文系コース全体のテーマである「学びを深める学びを学ぶ」ことを展望する講義でした。
辻教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。

第7回「経済発展と「学び」−インドでの「貧困と教育」調査から」2025.6.21(土)
佐々木宏准教授(教育学研究院)
世界のIT産業を牽引するグローバルエリートを多く輩出する経済大国インド。1990年代以降、経済が急成長し、2025年4月にIMFが発表したデータでは名目GDPが日本を上回り世界4位にランキングされました。今回の講義は、インドの都市ワーラーナシーをフィールドにする佐々木宏准教授が務め、インドの若者の貧困と教育をテーマに行われました。インドでは経済発展に伴い、進学率も高まりました。政府の統計データによれば、初等教育の就学率は100%、高等教育の就学率も2000年代以降急拡大し、2020年では、男女合わせて27%まで上昇してきています。教育熱が高まることは、受験競争の激化をもたらしました。統計的には女性の就学率も高くなる一方で、教育のジェンダーギャップは今なお大きく残っています。佐々木准教授は、ワーラーナシーで行ったインタビュー調査の結果を紹介し、インドで経済的に成功するためには学歴だけではなく、コネや家族の経済力など他の要素が必要になる可能性を指摘しました。「良い教育を受けることで豊かな生活ができるようになる」「教育は社会経済の発展に貢献する」という考え方を「教育の福音論」と言います。インドや日本でもこの考えは「あたりまえ」となっています。佐々木准教授は、この考え方が逆に社会の矛盾や問題を引き起こしつつあるのではないかと述べました。
佐々木准教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。

第6回「できない身体から学びを問い直す」2025.6.14(土)
山崎貴史准教授(教育学研究院)
私たちの生きている社会は「自分の力で、自分のことを、自分の身の回りの環境に合わせられること」を「できる」と捉えています。普通の人の「できる」ことが「できない」と「能力がない」と評価されることもあります。今回のテーマ「学習」は「できるようになること」と関係しています。確かに、自分一人できるようになることは大切なことです。しかしなぜそのことが、この社会では「能力」と結びついて評価の対象となるのでしょうか。山崎貴史准教授は障害者スポーツの事例を通じて、私たちがあたりまえだと考えている「できる」ことや「能力」それ自体を再編集する視点を提供します。障害者スポーツの特徴は、スポーツの用具やルールを参加者に合わせて変える点です。「スポーツの環境を変えて参加者が楽しめるようにする」のです。障害者スポーツは、個人よりもむしろ社会の側に障害の原因を見いだす「障害の社会モデル」の考え方と通じています。次に山崎准教授は自身が研究している、ブラインドマラソンを事例に「自分一人でできる」ことについて考えを広げました。ブラインドマラソンでは、目の見えないランナーが、伴走者とロープでつながり、一緒に走ります。このとき、私たちは、目の見える伴走者がランナーをリードすると考えがちです。しかし、実際に体験してみると、二者が協働して「走ること」や「見ること」を作り上げていることがわかります。私たちが自分の力で「できる」と考えていることも、振り返ってみれば、環境や技術や他の人との相互関係で成立しています。「二人でできる」ことは「自分一人でできる」こととは異なる、新しい体験や感覚を私たちに与えます。体育やスポーツは、自分とは異なる他者と共に活動することの豊かさや楽しさを経験できる機会になるのです。
山崎准教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。

第5回「読み能力の習得と発達性ディスレクシア」2025.5.31(土)
関 あゆみ教授(教育学研究院)
5回目の講義は、長年ディスレクシアの音読支援に携わってきた関あゆみ教授が担当しました。子どもの読みの発達と、読みが困難な人への支援が講義の柱です。子どもの読みの発達は個人差があるものの、大体4歳から5歳の間に文字が読めるようになります。読み能力の発達には段階があります。4歳から6歳の間に、それぞれの文字に音が対応することが分かるようになります。例えば「り」の文字には ri が「す」の文字には su の音が対応するといった具合です。この時期になると、子どもは言葉を1文字ずつ区切って読めるようになります。6歳から8歳になると文字を固まりで捉えて単語として認識して読めるようになります。例えば「り・ん・ご」と読んでいたものを「りんご」とまとめて流暢に話せるようになります。読みの能力の発達には、左脳にある特定の脳領域が関係しています。発達性ディスレクシアは学習障害のひとつで、脳機能の発達が要因となる、文字や単語の読み能力の習得困難が特徴です。読むことが困難なので、文字を書くことも困難になり学業不振につながることがあります。発達性ディスクレシアへの読みの指導は「発達の段階にそった指導をゆっくり丁寧に行うことが大事だ」と関教授は指摘します。第一段階として、文字と音の対応を確認し、文字を音に変換することを学びます。次に、単語の意味を確認して、まとまって読めるように語彙の指導を行います。関教授らが開発した「T式ひらがな音読支援(参考:https://t-shiki.jp/)」はその方法のひとつです。ディスレクシアだと気づくことができれば、合理的配慮に基づいて代替手段や補助手段を活用した学習支援を受けることができます。そのためにもディスレクシアの社会的認知を高めることが重要だと、関教授は講義を結びました。
関教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。

第4回「人間発達における乳幼児期」2025.5.24(土)
川田学教授(教育学研究院・北海道大学附属子ども発達臨床研究センター センター長)
今回の講義は発達心理学・保育学を専門とする川田学教授が担当しました。乳幼児期の子どもの発達について、人類の出産と現代社会、2つの視点から整理します。人間の赤ちゃんは他の霊長類と比べて大きな脳を持っています。一方で、二足歩行に適応した人間の母親の産道は狭いため、人間の赤ちゃんは産道を通れるように他の動物よりも未熟な状態で生まれくるようになったと考えられています。そのため、赤ちゃんは育つまでに時間がかかります。人類は、手のかかる赤ちゃんの育児を母親だけに任せるのではなく集団全体で行なってきました。「赤ちゃんが人びとをつなぐ」のです。また、赤ちゃんの脳は3歳ぐらいまでに急速に発達します。そのときの赤ちゃんは、外界で何が起きているかを知る認知機能の高まりに対して、身体を使って外界に働きかける移動運動機能の発達が追いつかない状況です。このギャップが埋まるのが2歳児だといわれています。2歳児は自分の身体を動かし能動的に身の回りを探索し始めることができるようになります。そんな子どもを大人は管理しようとして衝突します。これがいわゆる「イヤイヤ期」です。川田教授は大人が子どもを管理する先進国に「イヤイヤ期」に相当する言葉があることを紹介しました。社会のしくみや価値観が2歳児の捉え方に表れているのです。このように子どもと社会はつながっています。ゆえに子どもの成長を社会全体で支えるしくみが重要です。そのためには子育てを支える仕事の処遇改善が必要だと、川田教授は指摘しました。
川田教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。
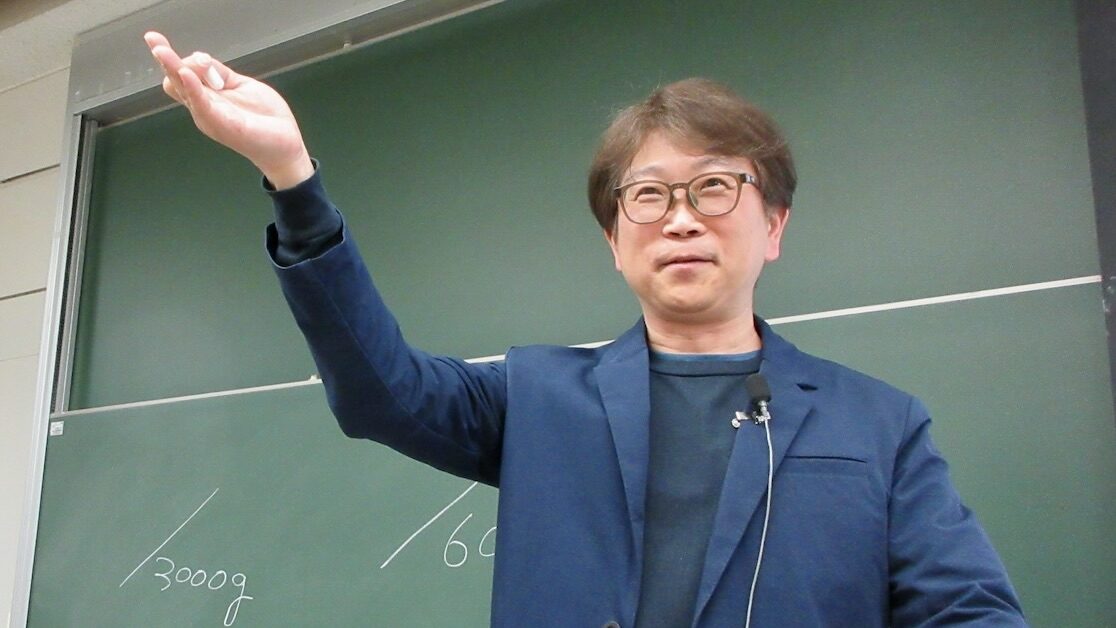
第3回「思春期になるとなぜ問題を起こせるようになるのか?」2025.5.17(土)
加藤弘通教授(教育学研究院)
今回の講師は発達心理学が専門の加藤弘通教授です。講義は【違う見方を知る】をキーワードに「発達とは何か?」「思春期とは何か?」について、参加者同士のディスカッションを踏まえて進行しました。加藤教授は「できなかったことができるようになる、良いこと」という一般的な「発達」の見方に対して【違う見方】を提示します。人間はおよそ9歳から10歳の間に「二次的信念」と呼ばれる「相手の気持ちを考える力」を身につけます。この時期に、いじめが深刻化するのは「相手が困ること」がわかるようになるからだと加藤教授は指摘します。人は発達することで「人を思いやれる」ようになる一方、置かれた環境によっては「いじめ」などの問題を「起こせる」ようにもなるのです。【違う見方を知る】と発達それ自体は良くも悪くもないことがわかります。また加藤教授は「思春期」に自尊感情が低下する要因の1つとして、思考の発達が批判的思考を可能にすることを挙げました。批判的思考が自分に向くと「悩んでいる自分に悩む」ことが生じ、結果として自尊感情が低下します。私たちは、思春期に不安定・不合理になるから自尊感情が低下すると考えがちです。これに対して加藤教授は、思春期に論理性・合理性が発達し、非論理的な権威に批判的になれるからこそ、自尊感情が低下するという【違う見方】を提示しました。大人は、思春期の問題行動に対して「子どもを変える」ことで対応しようとします。【違う見方を知る】ことで、子どもが置かれた「環境を変える」ことや「大人が子どもの理屈に耳を傾ける」ことの重要性に気づかされる講義でした。
加藤教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。
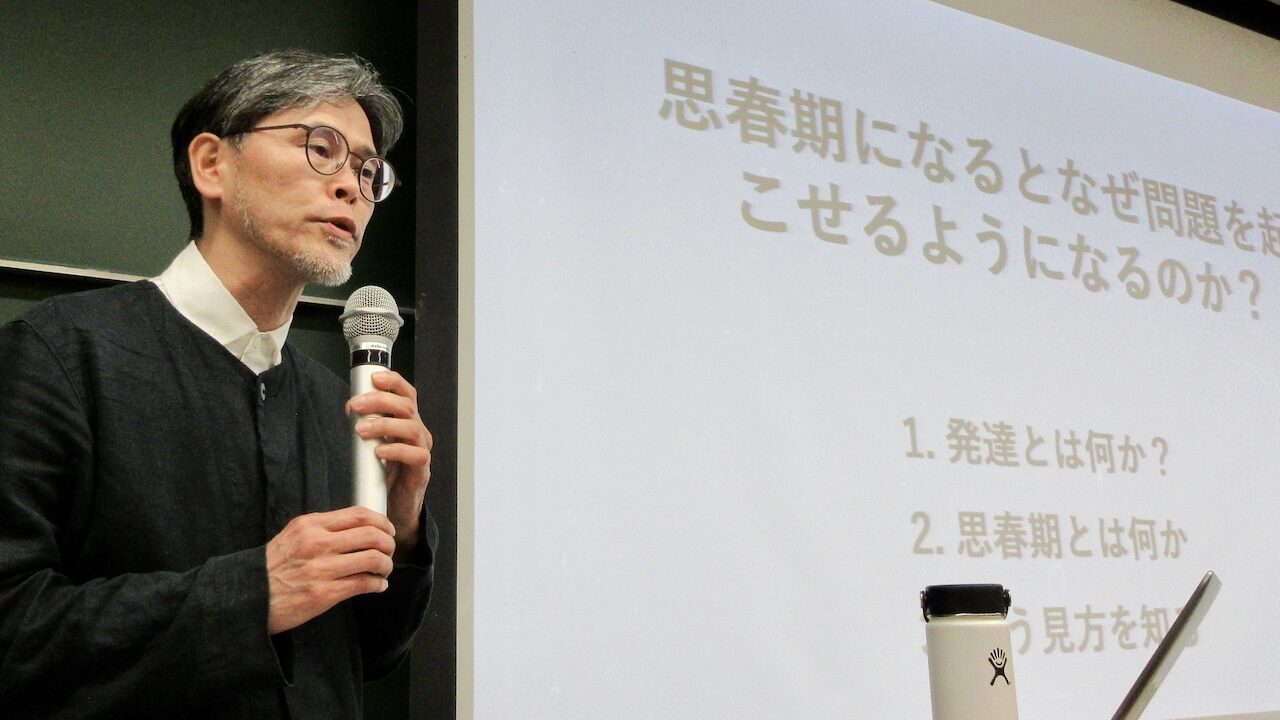
第2回「日本型公教育・学校システムにおける教育機会保障」2025.4.19(土)
篠原岳司准教授(教育学研究院)
2回目の講義は、教育行政学、学校経営論が専門の篠原准教授が担当しました。日本の学校教育制度と教育機会の保障がテーマです。教育を受ける権利の保障が、教育機会保障です。日本国憲法は、勤労・納税・教育を受けさせる義務を定めています。日本の就学義務制度は「一条校」への就学に限り、かつ、満15歳までを対象とした年齢主義を前提としています。「一条校」とは学校教育法第1条「学校の定義」に挙げられている、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校(小中一貫校)、高等学校、中等教育学校(中高一貫校)、特別支援学校、大学及び高等専門学校を指します。「一条校」制度は、私たちの教育を受ける権利を保障するための基幹となる制度です。一方で、今日の不登校者数の増加を見れば、従来からの「一条校」への就学の仕組みには限界が訪れている可能性があると篠原准教授は指摘します。そして、子どもの教育機会保障の将来展望として、一条校の制度を変革し、授業時間などを弾力的に運用することで包摂性を高め、より学校に通いやすくする方向と、一条校以外の教育機関へ、就学機会を開いていく方向の、2つがあることを提示しました。子どもたち誰もが等しく学び続けられる社会をつくっていくための根幹となる、日本の公教育制度について知ることのできる講義でした。
篠原准教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。

第1回「教育(education)の由来」2025.4.12(土)
白水浩信教授(教育学研究院)
初回の講義は「教育とは何か」を言葉の意味から考えていきます。担当する白水教授の専門は西洋教育史、教育思想史です。白水教授は、教育の原語であるeducationの元の意味が「能力を引き出すこと(drawing out)」といわれていることに疑問を抱きました。そこで「教育」の言葉の意味を語源から確かめていきます。教育の〈育〉あるいは〈毓〉は古代中国では「母が子どもを宿し、産む行為」を意味していました。また〈教〉と〈学〉は、共に「天と地を占いを通じてなかだちすること」を意味しています。現在では「教える」ことと「学ぶ」ことは対照的な意味ですが、漢字の語源としては一体のものだったのです。ではeducationの場合はどうでしょうか。ラテン語の語源educatioの古い意味は「栄養を与え養う」ことでした。〈育〉の語意に近いことが興味深いです。それがどうして「引き出す」ことになったのでしょう。白水教授は文献研究を通じてeducatioの元の動詞である、educareと似た、educereへ意図的に語源が書き換えられことを明らかにしました。educareの意味は養うこと、一方、educereの意味は引き出すことです。この書き換えによって、教育が、子どもをしつけ服従さることで能力を引き出すdisciplineの意味に転じていった可能性があると、白水教授は指摘しました。教育、educationの語源が、生命を養い育むことであり、現代のwell-beingの理念に通じていることは「学び直す」ことの意義をより深める知見だと感じました。
白水教授の講義の様子は北海道大学大学院教育学研究院のウェブサイトにも掲載されています。