実施報告:北大道新アカデミー2025前期理系コース
薬学研究の不思議な世界 薬学が創る新しい医療
北大道新アカデミーは、地域の「知」のために、北海道大学と道新グループが協力して2018年4月に開講した新しい学びの場です。2025年度前期理系コースは、北海道大学大学院薬学研究院の研究者が「薬学研究の不思議な世界 薬学が創る新しい医療 」と題して8回の講義を行います。
【講義概要】薬学研究院の8人の研究者が、身近な薬学研究が新しい医療を創る過程を語ります。日常の薬の背景にある最先端技術や研究、未来の医療についてわかりやすく解説します。がんや感染症、慢性疾患の最新治療法から次世代医薬品開発まで、薬学研究の魅力を幅広く紹介し、薬学が私たちの健康を支える仕組みを学びます。
【『北大時報』掲載】
・北大道新アカデミー2025年前期コース開催報告が『北大時報』2025年8月号16ページに掲載されました。
第8回「私たちの体を守る!ミトコンドリアとナノカプセルの未来」2025.6.28(土)
山田勇磨教授(薬学研究院)
本講義では、山田勇磨教授がナノカプセル技術が医療をどのように進化させるかについて解説を行いました。ナノは1ミリの1000分の1のさらに1000分の1の単位です。肉眼はもちろん、普通の顕微鏡では見ることができない大きさです。薬を必要な場所に必要な量だけ届け、必要な時間だけ作用させる考え方やそのしくみが、ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)です。山田教授の研究室では、ナノカプセルを用いたDDSの研究をしています。
講義の後半では、ミトコンドリアをターゲットとしたDDSについての解説が行われました。細胞の中にあるミトコンドリアの機能不全は、糖尿病や癌などの病気の原因になります。山田教授が特許を取ったDDSを用いると、細胞内のミトコンドリアに薬を届けて治療することができます。また、DDSと光線力学療法を組み合わせて、がん細胞のミトコンドリアを攻撃することで、がん細胞を倒す研究も進んでいます。クラウドファンディングを用いた研究活動についても紹介がありました。山田教授の研究や治療にかける想いが伝わってくる講義でした。
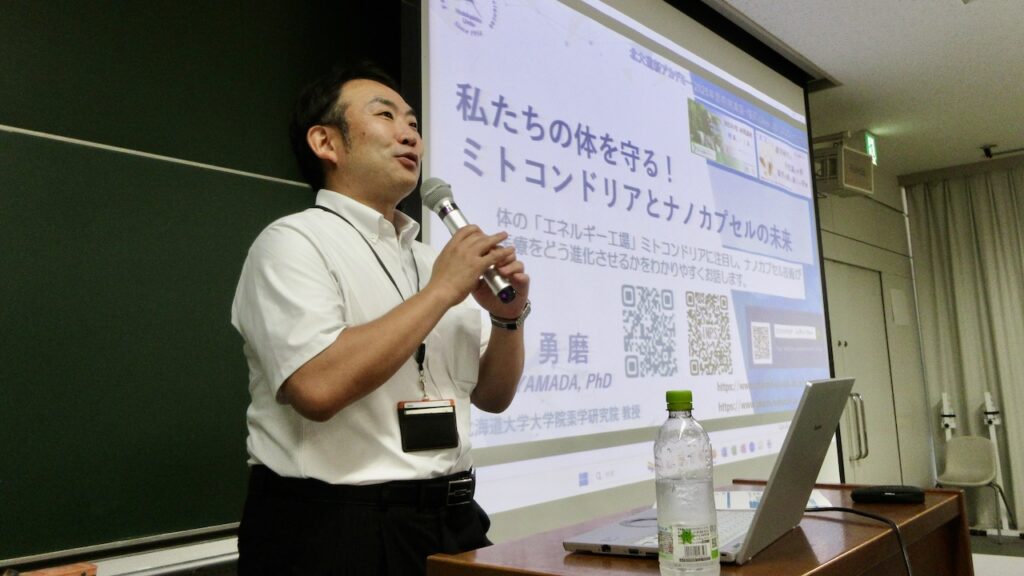
第7回「快と不快の脳科学」2025.6.21(土)
南雅文教授(薬学研究院)
本講義では、南雅文教授が「痛いこと」を「不快」に感じるメカニズムについて脳科学の観点から解説を行いました。快・不快の感情は脳内報酬系と呼ばれる神経機構が司っています。脳の中の腹側被蓋野と側坐核にあるドパミン神経の活動が、神経伝達物質のドパミンの遊離量をコントロールしています。ドパミンの遊離量が抑えられると不快を、逆に増えると快を感じます。
南教授は「痛み」が「不快」につながるしくみとして、脳の中の分界条床核に注目しました。痛みを感じると、分界条床核にある2型神経の活動が活発になります。この働きが、腹側被蓋野に伝えられ、ドパミン神経の活動を抑制することで、私たちは不快を感じます。痛みが慢性化するとドパミン神経が持続的に抑制されるので、抑うつ状態が続くことになります。講義では、脳内の特定の神経細胞を操作することで、人為的にマウスに不安を与える実験が紹介されました。私たちが痛みや快・不快を感じる脳のしくみの最先端を知ることができる講義でした。

第6回「自然から薬のタネを探す」2025.6.14(土)
吉村 彩 助教(薬学研究院)
自然界には、アオカビ由来のペニシリンや細菌由来のアベルメクチンなど、薬のもととなる天然化合物が数多く存在しています。講師の吉村彩助教は、そうした化合物を細菌から見つけ出す天然物化学の研究について紹介しました。
吉村助教は、約100種類の細菌に対し、他の細菌がつくる生体物質の影響を調べる実験を行い、その結果、影響を受けた細菌が化合物を生産することが明らかになりました。その中からは実用化された有効成分も単離されています。また、異なる細菌種同士が、化合物と生体物質によって互いを抑制し合うことも確認されました。
これらの成果から、細菌同士が天然物を介して影響を及ぼし合うネットワークの存在が浮かび上がってきました。吉村助教は、こうしたネットワークの理解が、細菌間の調和を重視した新しい創薬・治療戦略の構築につながると語りました。
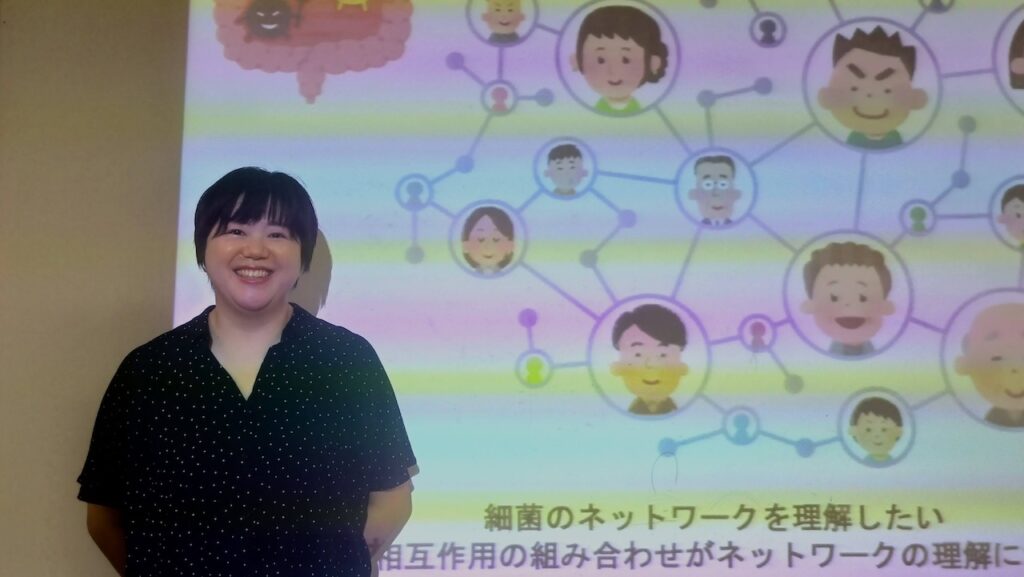
第5回「細胞を「くすり」として使う再生医療」2025.5.31(土)
大西 俊介 教授(薬学研究院)
本講義では、大西俊介教授が「細胞をくすりとして使う再生医療」について解説を行いました。再生医療とは、失われた臓器や組織の機能を回復させる医療であり、幹細胞や組織工学、自然治癒力を活用することで、新たな治療の可能性を切り拓いています。
講義では、骨髄や歯髄、羊膜などから得られる「間葉系幹細胞」が注目されており、炎症を抑制したり、損傷部位の再生を促したりすることが紹介されました。特に出産時に廃棄される「羊膜」から得られる幹細胞は、拒絶反応を起こしにくく、細胞の若さや増殖力に優れる点が強調されました。
後半では、実際に大西教授が取り組んできたラットモデルを用いた研究成果が多数紹介されました。心筋梗塞や肝硬変、炎症性腸疾患、内視鏡手術後の狭窄などに対し、羊膜由来幹細胞やその培養上清が、炎症抑制・繊維化抑制・組織修復に効果を示すことが実験的に確認されており、今後の臨床応用に期待が寄せられています。

第4回「くすりのリスク ~確かな情報を基にした、安全なくすりの使いかた~」2025.5.24(土)
小林 正紀 教授(薬学研究院)
本講義では、薬の正しい使い方や「飲み合わせ」によるリスク、さらに妊婦・授乳婦の薬物療法について、小林正紀教授が解説を行いました。薬の効果を保つには、用法・用量・服用間隔を守ることが重要であり、飲み合わせについては、牛乳やジュース、カフェイン、グレープフルーツジュースが薬の効き目や副作用に影響する可能性があることも説明されました。
後半では、小林教授の研究室による「メトトレキサートとプロトンポンプ阻害薬(PPI)の相互作用」や「ベンゾジアゼピン系薬物の母乳移行性」に関する研究成果が紹介され、基礎研究と臨床研究を融合させた、安全な薬物治療への取り組みが紹介されました。
講義に参加した受講生からは、日常的に服薬している薬の飲み方が正しいかを改めて見直しながら、身近なテーマとして講義に耳を傾けていました。

第3回「医薬品開発におけるタンパク質・抗体」2025.4.26(土)
黒木 喜美子 教授(薬学研究院)
今回の講義では、免疫抑制分子HLA-Gを活用した新たな医薬品開発の可能性が紹介されました。HLA-Gは妊娠時に胎児を母体の免疫から守る分子で、その仕組みを応用し、自己免疫疾患や炎症性疾患の治療に役立てる研究が進められています。HLA-Gには複数の構造があり、特にホモ二量体(双子状)になると免疫抑制効果が高まることが分かっています。かたちが異なるHLA-G2は、従来型に比べ低用量で効果を示し、関節炎やアトピー性皮膚炎モデルマウスでの症状軽減が確認されています。また、抗体医薬品の副作用について、抗体の構造や結合位置が細胞間距離に与える影響により、免疫シグナルが過剰に持続する可能性があるという構造的仮説も示されました。講義の最後には、HLA-Gのような分子ががん細胞にも利用されている現実に触れながら、ヒトの生命システムをくすりに活用する意義、そして副作用の少ない分子設計の必要性が強調されました。

第2回「新しい薬を創るとは?」2025.4.19(土)
乙黒 聡子 技術専門職員(薬学研究院)
新薬開発は、標的分子の探索から化合物スクリーニング、最適化、臨床試験、承認申請まで一貫した過程を経て進められます。開発には10〜20年、500億円以上を要し、約3万個の化合物からわずか1つが製品化に至る極めて困難な挑戦です。講義では、ハイスループットスクリーニング技術による候補化合物の選抜、動態(ADME)評価、安全性試験、特許戦略の重要性が詳しく紹介されました。特に新型コロナウイルス治療薬「ゾコーバ」では、北海道大学のBSL-3施設とクライオ電子顕微鏡によるウイルス構造解析が創薬を加速し、企業との共同研究により異例の4年で承認に至った過程が示されました。創薬は、科学技術と多分野の専門知識の結集により支えられています。

第1回「セラミドによる皮膚バリア形成」2025.4.12(土)
木原 章雄 教授(薬学研究院)
私たちの皮膚は、外的刺激や病原体から体を守る“バリア”として機能し、その最前線にある角質層では、セラミドを中心とした脂質ラメラが細胞間を埋め、強固な構造をつくっています。中でも「アシルセラミド」は、皮膚バリア形成に欠かせない特殊なセラミドです。セラミドの不足や異常は、アトピー性皮膚炎や魚鱗癬(ぎょりんせん)といった疾患に関係しています。魚鱗癬は、生まれつき皮膚が乾燥し、魚の鱗のように見える遺伝性疾患で、ELOVL1やCERS3 といった脂質代謝に関わる遺伝子の異常により、脂質ラメラがうまく形成されないことが原因です。木原研究室の実験では、Elovl1遺伝子を欠損させたマウスが生後すぐに重篤なバリア障害で死亡することが報告されました。
また、セラミドの種類と肌の保湿力・バリア機能の相関も研究され、基礎研究で得られた知見が薬の開発につながっています。
